株式会社瞬報社・瞬報社オフリン印刷株式会社 ─ 山口県下関市に本社のある印刷会社。冊子、カタログ、パンフレット、ポスター等、印刷から製本・仕分け発送まで何でもご相談下さい。
- HOME
- >
ニュース&トピックス
<<前 1 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次>>
2008年11月18日 山口県立防府西高等学校創立30周年記念式典の記念講演として秋山仁先生をお招きしました。
【写真印刷/本社】11月14日(金)、山口県立防府西高等学校様ご依頼の創立30周年記念式典の記念講演として、理学博士で数学者の秋山仁先生を、先月のアブニール学級に引き続き当社で手配をし、講演会の企画・運営のお手伝いをさせて頂きました。


演題「好きこそものの上手なれ」をテーマに講演されました。
先生が考えられた格言「才能は努力と共についてくる」を説明され、生まれつきの才能は関係ない、大きな志をたて、いろいろなことに興味をもち努力する事により自分流の横綱になれと説かれていました。講演中、聴いている高校生の皆さんも真剣で先生の熱意が通じたようでした。
ご自分のエピソードを交えたお話には、」ユーモラスなところなどもあり大変楽しい講演となりました。
今回の主催者である防府西高等学校の校長先生をはじめ教諭の方々には、大変お世話になりました。また、設備設置・運営を手伝っていただいた高校生の皆さま、大変有難うございました。


演題「好きこそものの上手なれ」をテーマに講演されました。
先生が考えられた格言「才能は努力と共についてくる」を説明され、生まれつきの才能は関係ない、大きな志をたて、いろいろなことに興味をもち努力する事により自分流の横綱になれと説かれていました。講演中、聴いている高校生の皆さんも真剣で先生の熱意が通じたようでした。
ご自分のエピソードを交えたお話には、」ユーモラスなところなどもあり大変楽しい講演となりました。
今回の主催者である防府西高等学校の校長先生をはじめ教諭の方々には、大変お世話になりました。また、設備設置・運営を手伝っていただいた高校生の皆さま、大変有難うございました。
2008年11月13日 グラフィックデザイナー急募!(瞬報社オフリン印刷)
2008年10月10日 下関市民文化セミナー「アブニール学級」に秋山仁先生をお招きしました。
【写真印刷/本社】10月5日(日)、下関市菊川町の菊川ふれあい会館「アブニール」において、下関市教育委員会主催「市民文化セミナー《アブニール学級》」として、数学者で理学博士、東海大学教育開発研究所所長、理学研究科教授としても教鞭を執られ、多くのTV・ラジオ番組でもご活躍中の秋山仁先生による講演会を、企画から運営まで弊社で執り仕切らせていただきました。


「発想の転換で不可能を可能に」というテーマで、常識を疑ってかかることから可能性が広がる数学の魅力、そこから見出す「人生をいかに生きるべきか」のヒントなど、発想の転換の重要性について約90分をかけてご講義いただきました。

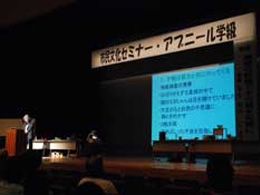
ステージには、教育開発研究所の所長として製作された様々な道具(教材)が並べられ、本や教科書でしか知らない理論や公式を、これらの教材を使った実験や検証で解説するなど、算数・数学嫌いな人でも抵抗無く聞き入ってしまったことと思われます。
その他にもスライドを使った数字のマジックや、アコーディオンの演奏なども披露されるなど、多くの方が驚かされたようです。





この数々の教材を使った実証実験では、時間の関係(先生は当日夕刻の飛行機で帰京されることになっていました)もあり、全てを紹介していただくことができませんでした。
また、準備機材の不調でお見苦しい点があったことをお詫びいたします。申し訳ありませんでした。
もっと沢山の話をお聞きしたかったとの声も聞かれ、次回からの反省材料とさせていただきます。


講演後には地元カモンFMの栗原世都さんのMCで質問コーナー、先生に当学級の生徒代表より感謝の意味を込めて花束の贈呈があり、そこでアブニール学級での講演会は終了となりました。
終演後には先生のご協力のもと、ロビーにおいて書籍販売を兼ねたサイン会を開きました。
先生のおかげで地元書店さんの用意した本はあっという間に完売してしまったようです。有難うございました。
先生、大変お疲れさまでした!

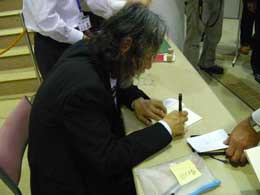
秋山先生は勿論のこと、聴講にお集まりいただいた皆様をはじめ、会を支えていただきましたアブニールの関係者の方々には、講演会が盛会の内に終えることができましたことに厚くお礼を申し上げます。
ご参加、ご協力いただき大変有難うございました。


なお、講演中でも先生から話をされていましたが、次回の山口県内での先生の講演は防府市の県立防府西高等学校で行われます。
しかし、この講演は同校の30周年を記念して行われるものですので、残念ながら一般の方の入場ができません。
ただし、弊社がサポートをさせていただく予定になっておりますので、このニュースコンテンツで当日の様子を紹介する予定です。


「発想の転換で不可能を可能に」というテーマで、常識を疑ってかかることから可能性が広がる数学の魅力、そこから見出す「人生をいかに生きるべきか」のヒントなど、発想の転換の重要性について約90分をかけてご講義いただきました。

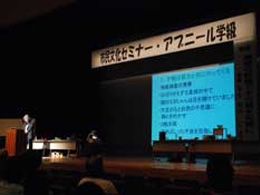
ステージには、教育開発研究所の所長として製作された様々な道具(教材)が並べられ、本や教科書でしか知らない理論や公式を、これらの教材を使った実験や検証で解説するなど、算数・数学嫌いな人でも抵抗無く聞き入ってしまったことと思われます。
その他にもスライドを使った数字のマジックや、アコーディオンの演奏なども披露されるなど、多くの方が驚かされたようです。





この数々の教材を使った実証実験では、時間の関係(先生は当日夕刻の飛行機で帰京されることになっていました)もあり、全てを紹介していただくことができませんでした。
また、準備機材の不調でお見苦しい点があったことをお詫びいたします。申し訳ありませんでした。
もっと沢山の話をお聞きしたかったとの声も聞かれ、次回からの反省材料とさせていただきます。


講演後には地元カモンFMの栗原世都さんのMCで質問コーナー、先生に当学級の生徒代表より感謝の意味を込めて花束の贈呈があり、そこでアブニール学級での講演会は終了となりました。
終演後には先生のご協力のもと、ロビーにおいて書籍販売を兼ねたサイン会を開きました。
先生のおかげで地元書店さんの用意した本はあっという間に完売してしまったようです。有難うございました。
先生、大変お疲れさまでした!

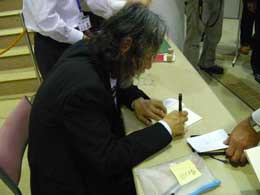
秋山先生は勿論のこと、聴講にお集まりいただいた皆様をはじめ、会を支えていただきましたアブニールの関係者の方々には、講演会が盛会の内に終えることができましたことに厚くお礼を申し上げます。
ご参加、ご協力いただき大変有難うございました。


なお、講演中でも先生から話をされていましたが、次回の山口県内での先生の講演は防府市の県立防府西高等学校で行われます。
しかし、この講演は同校の30周年を記念して行われるものですので、残念ながら一般の方の入場ができません。
ただし、弊社がサポートをさせていただく予定になっておりますので、このニュースコンテンツで当日の様子を紹介する予定です。
2008年7月29日 文芸誌「燭台」の第4号を5年ぶりに刊行いたしました。!!
約5年振りに総合文芸誌「燭台4号」が発刊されました。「燭台」は、戦前、詩人・ジャーナリストとして活躍した吉田常夏が山口県下関市で発行し(昭和2年~7年)、地方発の文化発信の新しいスタイルとして評価された文芸誌「燭台」を、直木賞作家・古川薫氏(下関市在住)が中心になって復刊をしたものです。
「燭台4号」では、その古川薫氏を中心に、高見順賞受賞詩人・北川透氏、文藝賞受賞及び芥川賞候補作家・後藤みな子を始め、幅広い分野の方々の寄稿を得て編集・発行をしております。
今回の特集では、映画名”無法松の一生”(原作名:富島松五郎傳)で知られている北九州の作家、岩下俊作を取り上げました。また、サブ特集には江戸時代の女流文人、田上菊舎の顕彰をいたしました。4号の内容は以下の通りです。
【内容】 →「燭台」目次PDFはこちら
<詩> 亀裂についてのノート 北川 透
<短歌> 万愚節 石田比呂志
<俳句> あづまはや 上野 燎
<特集対談> 九州文学と岩下俊作 星加輝光(故人)・佐木隆三・古川 薫・後藤みな子
岩下俊作年譜
岩下俊作の小説作法 八田 昂
無法松幻影 川﨑加奈子
刻を超えて 堀 晃
<史談> 楊貴妃漂泊 古川 薫
詩と詞・あねいもうと 石川 秀
江戸好み鯨の彩々 和仁皓明
田上菊舎十句鑑賞 長戸幸江
<対談> 雲遊の尼・田上菊舎 岡 昌子・諸井耕二・山本健一郎・清永唯夫
燭台・常夏・下関(後篇) 吉田静代(故人)
山口旅館と西洋館 富田義弘
藤棚 後藤みな子
「燭台」は、地域文化の振興・発展のためにも定期的に発行してゆきたいと願っております。これからも山口、北九州を中心に、様々な方々の協力を得ながら良質な総合文芸誌を制作し続けたいと考えております。ご声援の程、宜しくお願いいたします。
編集人 藤田育夫
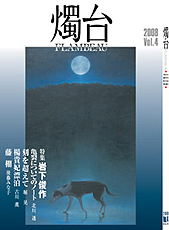
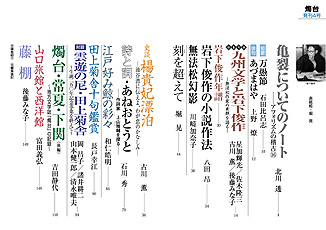
先日(7月25日)に「燭台4号」発行を祝う会を催しました。皆さん、次号発行へ向けて「燭台」の灯を燈し続けようと決意を新たにしました。写真前列左から、北川透さん、古川薫さん、清永唯夫さん、後藤みな子さん、後列左から、富田義弘さん、要田二三子さん((株)こがた)、森重香代子さん、川﨑加奈子さん、藤田育夫(燭台編集人)、八田昂さん、石川秀さん、佐々木正一さん(山口新聞特別編集委員)です。
 →画像をクリックすると拡大表示します。
→画像をクリックすると拡大表示します。
「燭台4号」では、その古川薫氏を中心に、高見順賞受賞詩人・北川透氏、文藝賞受賞及び芥川賞候補作家・後藤みな子を始め、幅広い分野の方々の寄稿を得て編集・発行をしております。
今回の特集では、映画名”無法松の一生”(原作名:富島松五郎傳)で知られている北九州の作家、岩下俊作を取り上げました。また、サブ特集には江戸時代の女流文人、田上菊舎の顕彰をいたしました。4号の内容は以下の通りです。
【内容】 →「燭台」目次PDFはこちら
<詩> 亀裂についてのノート 北川 透
<短歌> 万愚節 石田比呂志
<俳句> あづまはや 上野 燎
<特集対談> 九州文学と岩下俊作 星加輝光(故人)・佐木隆三・古川 薫・後藤みな子
岩下俊作年譜
岩下俊作の小説作法 八田 昂
無法松幻影 川﨑加奈子
刻を超えて 堀 晃
<史談> 楊貴妃漂泊 古川 薫
詩と詞・あねいもうと 石川 秀
江戸好み鯨の彩々 和仁皓明
田上菊舎十句鑑賞 長戸幸江
<対談> 雲遊の尼・田上菊舎 岡 昌子・諸井耕二・山本健一郎・清永唯夫
燭台・常夏・下関(後篇) 吉田静代(故人)
山口旅館と西洋館 富田義弘
藤棚 後藤みな子
「燭台」は、地域文化の振興・発展のためにも定期的に発行してゆきたいと願っております。これからも山口、北九州を中心に、様々な方々の協力を得ながら良質な総合文芸誌を制作し続けたいと考えております。ご声援の程、宜しくお願いいたします。
編集人 藤田育夫
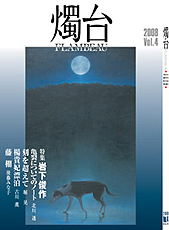
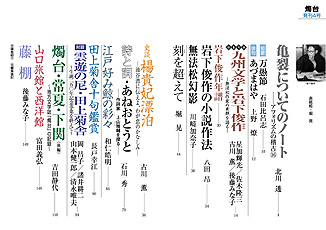
先日(7月25日)に「燭台4号」発行を祝う会を催しました。皆さん、次号発行へ向けて「燭台」の灯を燈し続けようと決意を新たにしました。写真前列左から、北川透さん、古川薫さん、清永唯夫さん、後藤みな子さん、後列左から、富田義弘さん、要田二三子さん((株)こがた)、森重香代子さん、川﨑加奈子さん、藤田育夫(燭台編集人)、八田昂さん、石川秀さん、佐々木正一さん(山口新聞特別編集委員)です。
 →画像をクリックすると拡大表示します。
→画像をクリックすると拡大表示します。 2008年6月11日 下関市上下水道局主催 平成20年度「水道展」企画運営報告!!
【写真印刷/本社】シーモール下関(1Fコンコース・2Fサンパティオ)及び長府浄水場において下関市上下水道局主催 平成20年度「水道展」を企画から運営まで弊社で執り仕切らせていただきました。
私たちの生活に密接に関係した上下水道、下関市上下水道局が担う3A/安心・安全・安定のサービスを広く市民の方々に理解と関心を深めていただく為に企画された催しです。
弊社が取り扱っているレンチキュラーによる水道の蛇口イメージが彩りを添えています。




「水を楽しむ」をテーマにシーモール正面玄関・2Fサンパティオの2会場で市民ミュージカルの皆様によるタップダンスを「雨にうたえば」「雨にぬれても」のなつかしの名曲をバックに披露していただき絶妙なタップに観覧の方々も興味しんしん


「水と親しむ」をテーマに近年マスコミでも紹介された神秘の魚「ドクターフィッシュ」を紹介しました。
人間の古い角質を食べる習性があり皮膚病の治療にも用いられている魚です。来場して頂いた皆様も交互に水槽に手を入れられ不思議な感覚を体験して頂きました。




「水と命」をテーマに「ハーブ&アロマと香りの店」代表 竹内栄子さんを講師に招き「オリジナルテラコッタ作りとスプラウトの種植え教室」を行いました。


1Fコンコースにて下関市内各企業さまが環境に配慮した取組みをパネルにて展示いたしました。
弊社の環境への取組みについても併せて展示させて頂きました。


この度、参加頂いた皆様、またご協力頂いた方々ほんとうにありがとうございました。
私たちの生活に密接に関係した上下水道、下関市上下水道局が担う3A/安心・安全・安定のサービスを広く市民の方々に理解と関心を深めていただく為に企画された催しです。
弊社が取り扱っているレンチキュラーによる水道の蛇口イメージが彩りを添えています。




「水を楽しむ」をテーマにシーモール正面玄関・2Fサンパティオの2会場で市民ミュージカルの皆様によるタップダンスを「雨にうたえば」「雨にぬれても」のなつかしの名曲をバックに披露していただき絶妙なタップに観覧の方々も興味しんしん


「水と親しむ」をテーマに近年マスコミでも紹介された神秘の魚「ドクターフィッシュ」を紹介しました。
人間の古い角質を食べる習性があり皮膚病の治療にも用いられている魚です。来場して頂いた皆様も交互に水槽に手を入れられ不思議な感覚を体験して頂きました。




「水と命」をテーマに「ハーブ&アロマと香りの店」代表 竹内栄子さんを講師に招き「オリジナルテラコッタ作りとスプラウトの種植え教室」を行いました。


1Fコンコースにて下関市内各企業さまが環境に配慮した取組みをパネルにて展示いたしました。
弊社の環境への取組みについても併せて展示させて頂きました。


この度、参加頂いた皆様、またご協力頂いた方々ほんとうにありがとうございました。


